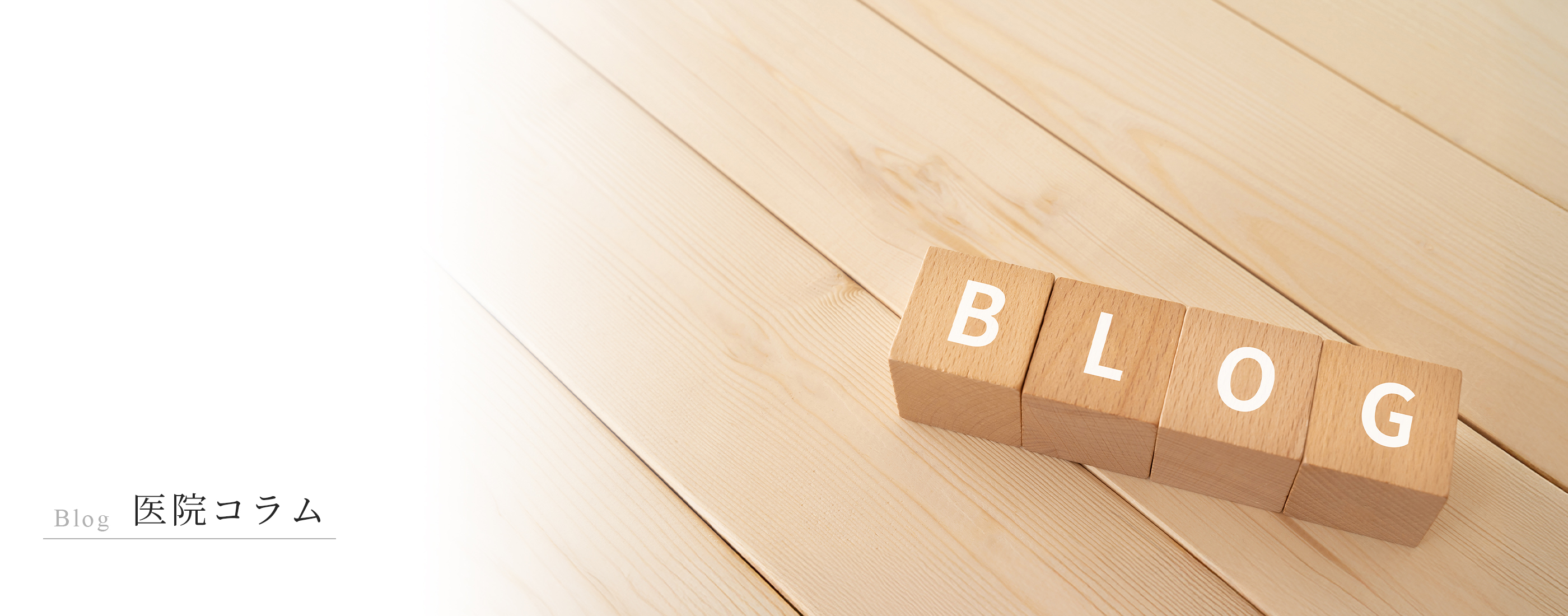
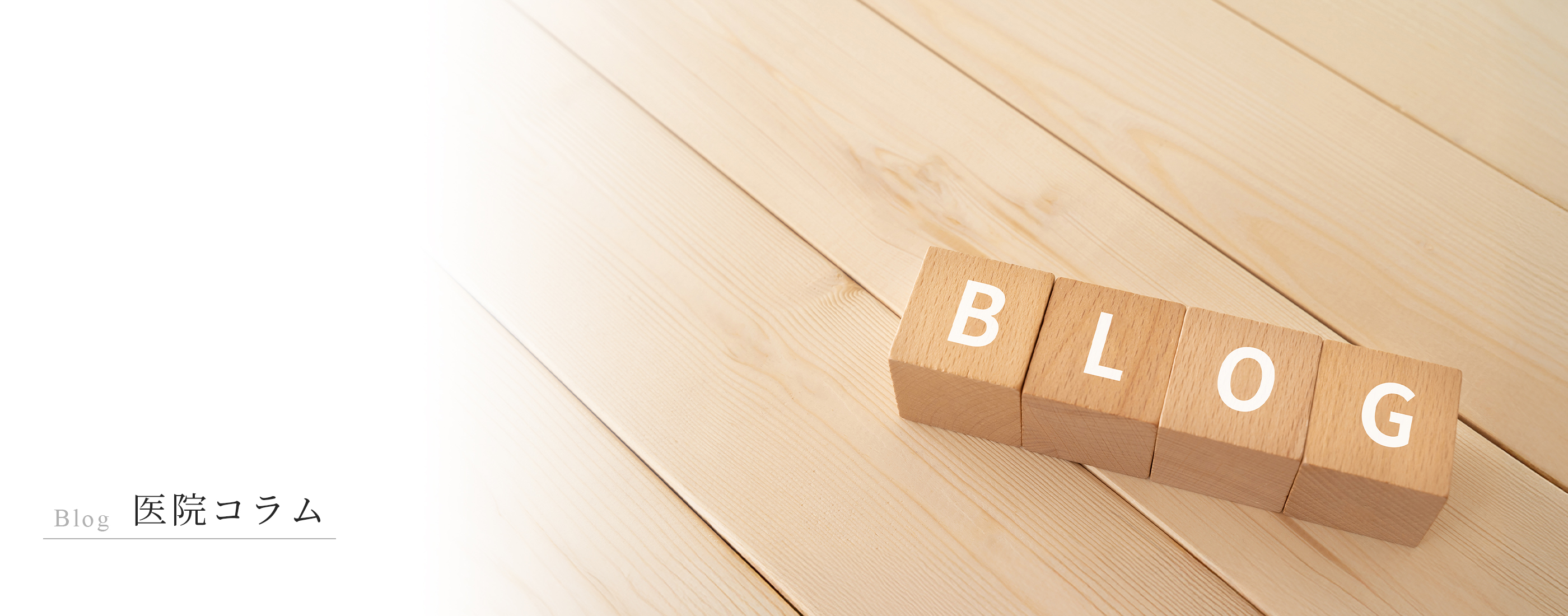
2022年11月15日
今回は、この二つの病気がどのように関連しているのか、また、どちらも重症化させないためにどんなサインに気をつけたらいいのかということについてご紹介します。

糖尿病にかかると、網膜症、腎症、神経障害などの合併症が起こることが知られていますが、そのほかにも脳梗塞や心筋梗塞に加え、歯周病などの感染症にかかりやすくなることもわかっています。
歯周病を発症すると、炎症性物質が血管の中に入り込み、血糖をコントロールするインスリンの働きを妨げ、糖尿病を悪化させることがわかっています。
それでは、両者の初期のサインとは何なのか?その一つのサインとして「歯茎の出血」が挙げられます。
歯茎の出血は、たまに出るものであればそれほど問題はありませんが、頻繁に出血がある場合や、簡単に出血しやすい場合、注意が必要です。
歯茎から簡単に出血する場合、歯周病による炎症が強い状態だと言えます。歯周病の程度が軽度であれば、歯磨きをきちんと行うことで落ち着くこともありますが、歯周病が進行した状態や歯石が多くついている状態だと、それだけでは治すことは難しく、歯科での治療が必要になります。多くの場合、プラークコントロールを中心とした歯周病の治療を行えば炎症が治まってきます。
でも中には、プラークコントロールをしても、なかなか歯茎の炎症が落ち着かない、ということがあり、そのような場合には、糖尿病により血糖値が高すぎることが原因で、歯茎の炎症が落ち着かない、ということがあります。血糖値が高いと、歯周病の治療をしても、なかなか効果が現れず、赤く腫れたままの出血しやすい歯茎の状態となってしまうのです。
歯茎の出血がなかなか落ち着かない場合には、まずは歯科を受診し、まず歯周病治療を受けることが大事です。しかし、どんなに治療を進めても出血が落ち着かない場合には糖尿病を疑ってみたほうが良いケースもあります。もちろん、糖尿病だけでなく、他の疾患が疑われることもあります。
「歯茎から出血しやすい」、という症状のある人は、放置せず、まずは当院までご相談ください。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。